仕事で成果を出し始めると上司から問われるのは「お前の考えは何だ!」だったりします。
誰かの意見や考え方の受け売りではなく自分自身の思いや意見を問われるわけです。
見方を変えれば、それだけ信頼を寄せて貰えてるとも言えますかね。
その様に信頼や責任の量も増していく中で個人の意見を
アウトプットしていくには、ここで紹介する本がとても役に立つ!
この本のおかげで自分で考えることの重要性を知ることに繋がったんです。
2011年に20年以上勤めた会社を辞めて異業種へ転職(今の仕事)するときに
「仕事に集中するため自己啓発本の読みあさりは、いったん中止しよう」
と思いたち半ばがむしゃらに日々を過ごしてきました。
そのおかげもあって坪単価90万円以上もする注文住宅の住宅営業マンになった
最初の1年で13件の契約を頂くことができたのかもしれませんね。
(本を読んでいる時間すらなかったというのが本音かも(^^;)
そうこうしているうちにようやく住宅営業マンになってから
時間に少しずつ余裕が生まれ始めたのが、ここ最近の状況です。
時間が生まれたことで数か月間は、市立の図書館へ行こうと思い
通っていました。そこでこの本と出会いました。
前置きが長くなりましたが、この本は書評で良書の評価が多かった点も
読んでみたいと思ったきっかけです。
さらに一度借りに行ったときに図書館では、貸し出し中で1回待った
というのも読みたい感を高まらせてくれた要素の一つです。
自身のLifeHack指南書として書き留めておきたいと感じたので
自分なりにまとめてみました。
他の方にも何かの参考になればうれしいです。
「知識」は過去、「思考」は未来!

このセンテンスにグッと来てしまいまいました!
日本人は、世界から見ても保守的な人種ということで
今の生活ややり方を変えるのを嫌う傾向にあるそうです。
確かに自分でもそう感じることがあるし職場のメンバーを
見ていても多くの人は、新しいことに否定的ですね。
よく知らない分野であれば、革新的なアイデアを寛容に受け入れる人も、自分の専門分野については驚くほど保守的であったりします。
保有する知識が多過ぎてどんなに斬新なアイデアを聞いても頭の中から引っ張り出してきた知識によって「そんなことは不可能だ。出来るわけがない」と否定してしまうからです。「詳しくなればなるほど、その分野での新しいアイデアに否定的になる」傾向が見られたら「知識が思考を邪魔している」ことを疑ってみるべき
組織が求めるあるべき姿は、豊富な知識を用いて新たなアイデア創出や
改善・効率化に力を使ってほしい的な事だと思いますが
いざそれをやろうとすると時間も労力もリスクも伴うので
保守的、否定的になるのも仕方ないのでしょう。
前の会社では、考えるよりまず行動をと言われ
「50%スタート(半分できそうだと確認できたらそれ以上考えるより行動へ)」
を常に言われてました。
結果も大事であるが、取り組もうとする姿勢や結果へのプロセスを
評価するよという意味もありました。
その会社を辞めて4年ほど経ちますが、結構いい会社だったかもと思う時があります。
そして本にも出てきますが、情報化社会の今は、昭和と比べて
時の流れが早いと言われています。そう言った変化のスピードに
耐えうる人材が大事にされるわけです
反対に思考力のある人は、自分の専門分野においてさえ革新的で柔軟です。
それは彼らが常にゼロから考えているからです。時代が変わり世の中が変わり新しい現象が出てきて新しい情報に触れた時、過去の知識ではなく目の前の情報から考えることができるかどうか。
それが「考えることが出来る人」とできない人の分岐点です。もしくは「時代の変化に気がつく人」と気がつかない人の違いとも言えます。
そしてポイントは
「思考力=未来を考える力」
私は昔から妄想族なのである意味思考力は高いのではと勝手に思っています。
その妄想力を思考力に変えてやっていこうと決めたほどです。
そして思考力を意識していると沢山のデータや情報に
接しいつしか思考力が低下します。そういったときは
「三上《欧陽脩「帰田録」の「余、平生作る所の文章、多くは三上に在り。
乃(すなは)ち馬上・枕上(ちんじゃう)・厠上(しじゃう)なり」から(コトバンクより)」
を実行していましす。トイレ(厠)に行くと狭い空間なので一旦情報が遮断されます。
すると思考力が増して原点回帰的な発想やシンプル化の発想へアタマが働き
「気づき」
が生まれたりします。
なのであまりおしっこしたくなくても仕事で行き詰っときは
気づきや発想の転換を求めトイレに行くようにしています!
また知識の中で特に影響が大きいのは、成功体験と結びついた知識です。
過去に大成功したという記憶(それ自体がひとかたまりの知識です)が、新しい情報に触れた時にしゃしゃり出てきてゼロから考えることを妨げます。
そうなるとせっかく時代の変革を期に新しい情報に触れているのに過去の知識に囚われてしまい先入観をもたずに考えることができなるなります。
ほかの多くの成功本でも成功するためには、成功体験をたくさん積もう!

というのは、常套手段して出てきます。
ここではそれを一つの塊の知識としている点、面白いなぁと感じました。
小さな成功体験をパケット(小包)のようにイメージして
それをいつでもと取り出せるようにしている
(ノートに書いたりスマホでメモに残したりなど)
自分に合った知識の塊を取り出す方法を決めておくといいかもです。
思考の過程において自分の考えを「まずは言語化し、次に視覚化する」二つのステップで検証することにより自分の考えの甘かった部分が見つかり思考をより深めることができる。
イメージの言語化、具現化
定性⇒定量化
データ⇒情報化
このように別の誰かと正確なコミュニケーション
やり取り(特に仕事では)をする際には、
具現化や定量化がキーになりますね。
あとで自分自身が見直す時でもわかりやすいですしね。
終章
「考えるためには知識と思考を区別することが重要」
上司への報告やプレゼン用の資料を作る際には
「事実」と「意見」を区別せよ!とよく言われたものです。
今では、それを注意する側ですが、自分でも普段からこの点を
多少なりとも意識しています。
そうすると不要な混乱を避けることにもつながるのでこの点大事にしていきたいですね。
知識と思考についても同じような関係性があるんだなと知りました。
知識はしばしば思考の邪魔をすることがある
ちきりんの考える「知識」と「思考」の最適な関係は
「知識を思考の棚に整理する」というもの。
棚については、頭の中で作って使うというよりは、
ノートやスマホアプリを使って具現化して実体化しておく方が
長くそしてより正確に整理、使用できると思います。
思考の棚の中に知識を整理して入れ込むことにより、個別の知識が意味を持ってつながり、全体として異なる意味が見えてくる。
このような「統合された知識から出てくる新たな意味」が、「洞察」と呼ばれるものとなる。
洞察、洞察力大事ですね。
枝葉末節にとらわれすぎたり木ばかりを見ていると
森が見えなくなる思考にもつながるので
より洞察力を生かすなら「俯瞰力」「マクロ視点」も併せ持つと

もっといい結果につながると思います。
「同じものをみても、いろいろと気がつく人と、ぼーっとしていて何も気がつかない人がいる」という言い方をしますが、この両者の差は、「知識を整理するための思考の棚を持っていて、次に知りたい情報を意識的に持っているかどうか」にあります。
「思考の棚」を用意しどの棚にどんな情報が入っているか、空いている棚はどんな棚で、自分はその棚にどんな情報を欲しているか。そこを意識していないと、実際にそれらの情報に触れても気づかずに見過ごしてしまう。
社会に出て働き始めるとこのような「気づき」の大事さを痛感します。
そして気が付く人が行動力を持つととても頼りになる存在になります。
その結果が、サラリーに反映されると考えれば、ちきりんさんの言う
「思考の棚」の大事さは言わずもがなですね。
仕事で大事にしなければならない4つ
「人・もの・金・情報」
昔は「人・もの・金」の3つでしたが、何年か前からは
そこに「情報」が追加されました。
「自分のアタマで考えよう」で情報の大事さを再考したので
自分でも思考の棚を整理しようかと思い立っている今日この頃です。
皆さんは、いつ整理しますか?(←今でしょ!ってそろそろ古いかな)
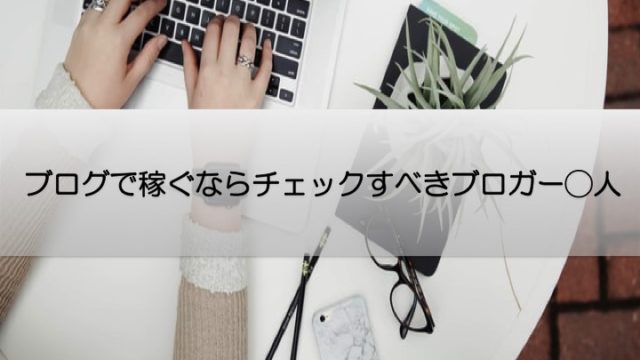
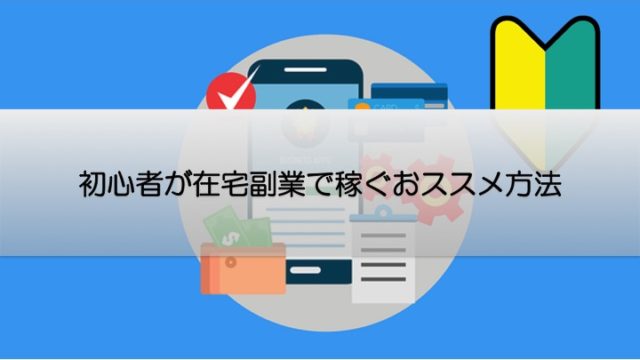
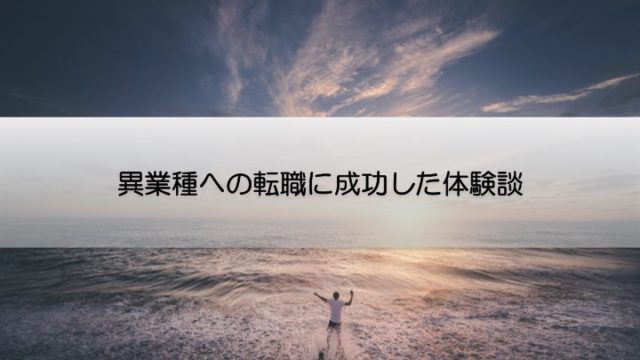











コメント