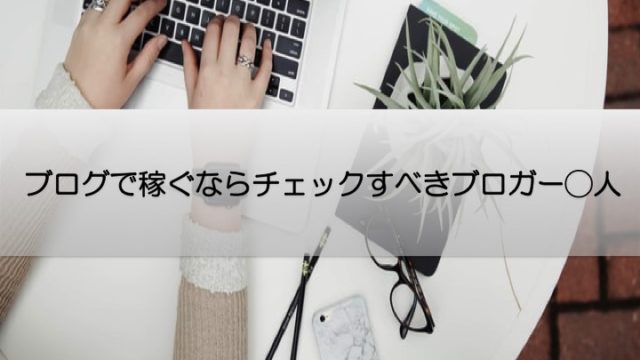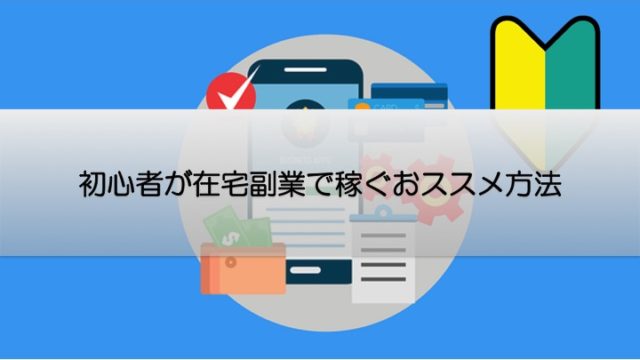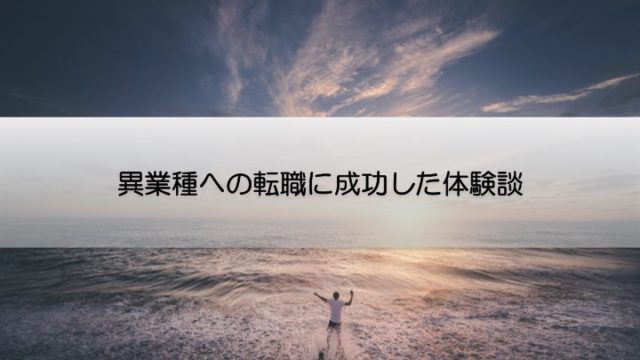多くの方が関わった経験あると言っても過言でないハラスメント系人間。
特に仕事面で退職の理由No.1が「人間関係」。その背景にはこのハラスメントが少なからず関係していることでしょう。
あなたの職場にも問題ありな悩ませ男、悩ませ女。
もしくは、朝令暮改は当たり前!どころかさっき言ってた事と今言ってる事、どっちやねん❗️て心の中で大声でムンクの様に叫んでしまうあいつ‼️
自分自身も2020年6月現在、ハラスメント全開の上司と一緒に仕事をしています。
仕事の場合は、従属関係があるので関わらない訳にいかないのが厄介なところ。
今回は、相手との関係ですれ違いや話が噛み合わない等の現象がなぜ起こるのかについて「具体と抽象」のキーワードから分かり易く書かれている本の紹介です
この本はトレーニングとある様に途中に演習問題がいくつか含まれているため具体的なイメージがしやすい構成になっています。
過去には基本編として以下の著書があるので興味がわいた方は是非、深く知ってください!
この本を読んだ事で自分の中の一つのモヤモヤがはれたと感じたので本の内容でポイントになる部分とモヤモヤがどうはれたのかについて書いてみようとおもいます。
まず本の目次は以下となります
- なぜ具体と抽象が重要なのか
- 具体と抽象とは何か?
- 抽象化とは?
- 具体化とは?
- 「具体⇄抽象ピラミッド」で世界を眺める
- 言葉とアナロジーへの応用
- 具体と抽象の使用上の注意
「具体」にしても「抽象」にしても普段よく聞く単語ですね。これら2つの言葉の意味をより深く理解、知る事で冒頭に書いたようなハラスメント系(クソ)上司とのコミュニケーションエラーを最小限に抑えることができるんです。
「具体と抽象の違い」から生まれるコミュニケーションのギャップ
著書の例にもでてきますが「言うことがコロコロ変わる上司」「SNS上での対立」「言葉の違いによるコミュニケーションギャップ」これら日常でよくありがちな事は
「具体と抽象」の視点の欠如が重要な要因!
お互いが「具体と抽象」の視点をもっていないから自分も上司とコミュニケーションのギャップが生じる訳です。
カンの良い人ならもう結論的なイメージができてしまうかも知れませんが、この気付きを得るだけでその後の人間関係が変わって来るやもです。
著書に戻りますが、多くのコミュニケーションの場面で共通する悪状況に「理解できない」があります。
その代名詞として「抽象」と言うものがありますね。その対極に「具体」がある。「抽象的で分かりにくいのでもっと具体的に言ってくれ!」的なやつです。これがギャップな訳です。
そのギャップが起きてしまう原因について簡単には、以下の様な性質の違いがあります。
抽象とは

- 集合
- 一般
- 五感で感じられない概念
- 二者以上の関係性、構造
具体とは

- 個別
- 特殊
- 五感で感じられる実体
- 個々の属性(形、色、大きさ、など)
上記のように抽象と具体の言葉には、性質の違いが存在すると言う訳です。これは例になりますが、この項目で違いは明らか。よって日々の仕事に置いて考えると
上司は、部下にこれで通じると思い抽象的な指示をするが、部下はミスした時の責任問題もある(特にパワハラ系上司の場合)ので具体的な指示を待っている。
この上司側(抽象でOK)、部下(具体待ち)の状況がコミュニケーションギャップの生じる要因イメージなのです。
上司も部下も「具体と抽象」の視点無きままコミュニケーションをしていると多くのギャップが生まれやすくなる訳です。話が噛み合わないわけです。
ここまでで私の中の上司との会話にギャップが生じる理由が分かったんです。
著書の中で「具体と抽象」についてもっと詳しく体型的に描かれていますが、日常的な事象にあわせるとこの様なイメージかと
簡単にまとめましたが、これだけではじゃぁどーすりゃいいの?ってなってしまうので、日頃グランドキャニオンの如く多数のギャップを感じるわけですが、それを回避するための方法がいくつか書かれているので紹介します。
コミュニケーションギャップを回避する方法
冒頭の「具体と抽象」の視点をもつ事はもとより、これを知るだけでも大分相手とのコミュニケーションに変化がでると思いますが著書では以下についても書かれています。
「座標軸を持つこと」が何より大事!
本書で論じてきたコミュニケーションギャップが生じる原因は、「具体化や抽象化ができるかどうか」ではなくて、そもそも「具体と抽象と言う視点を持てるかどうか」そして「その中で今行われていることがどこなのかをマッピングできるかをその軸上にマッピングできるかどうか」ということ。
著書より
それぞれの発言を一歩引いた位置から見る、鳥の目を持って上空からの視点で見ることができれば不毛な時間のロスも減らせますね
「前提条件を明確にすること」の重要性
抽象化とは「都合のいいように切り取ること」(中略)切り取った側もそれを聞かされた方もその事に気づいていないために、それがコミュニケーションギャップの大きな要因になっていることは5章で示した通り。したがってこれを回避するための手段は明確です。「どういう条件の下で」「どのような目的で」といった前提条件を明確にしてから言葉を使ったり説明の内容を確認したりすれば良いということです
仕事の場でコミュニケーションギャップを無くすには、上記前提条件の対策が有効ですね。自分が話すとき上司から話を聞くとき「前提条件」を明確にしてから話をするとギャップレスもできそうです。
この切り取りに関しては、最近のマスメディアは当たり前のようにやってますね。しかも恣意的であり前提条件も無しに。そのような状況でTVというメディアを使ってさらに偏向のオマケ付きとなれば、伝える側(大元)と聴く側の間に大変大きなギャップが生じているという事になるのかと。。。怖っ!
抽象から具体はマジックミラー
抽象の世界は「見える人にしか見えない」からです。逆に具体の世界は誰にでも見えます(それが具体の定義なので)から、抽象が見える人(正確に言えば具体も抽象も見える人)から具体しか見えてない人は見えても、逆はそうでないからです。
抽象表現で通じ合えるっていわゆる以心電信に近いものでお互いをある程度理解している間柄でないと難しいですよね。少ない言葉で分かり合える関係(夫婦や恋人、幼なじみ等)のレベルに逹すると地球にも優しくコスパの良いスペシャルな関係になり仕事もプライベートもうまくいきそうですね。今の上司とは一生わかりあえなそう😓
抽象化が得意な人はなぜ人の話が聞けないのか?
抽象化レベルで物事を捉えるている人にとっては、日常の様々な話が全て「どこかで聞いた話」になってきます。サッカーの話と演劇の話と職場の人間関係の話が「全て同じ構造」だと見抜いてしまえば「またあの話か」となるわけです。こうなれば、なぜそうした人たちが他人の話を聞くのが苦手になるのがお分かりでしょう!(中略)
抽象化能力が高い人は、周囲からは「飽きっぽい人」と見られます。(中略)抽象能力が高いと、他の人にとっては別の事をやっているように思えることが、全て「ドリル」のような単純作業を繰り返す行為に見えてしまう
身近にこういう人、居ますよね。こういった事実を知った上で相手を見ることができれば、要らぬ心配や気遣いの方法も変わってきますね。何事においてもそうですが、この程度の事を知らないだけで、心と身体を浪費していると思うと知ることの大事さを痛感します。情報を取りに行く事は自分にとって大事なのです!行動する人が成功すると云われる所以はこういった小さく身近な日常に溢れているという事なんです。
読書と「具体と抽象」との関係
著者が本書やこれまでの著作で心がけて来たのは「伝えたいのは常に抽象化した汎用性の高いモデルの方だが、それを説明するのに必ず具体例を用いる」という事です。(中略)
本書で読者に期待していること、逆に言えば「そのような期待をもって本書に臨んでいるはずだ」と筆者が想定している読者は、本の具体例から抽象モデルを理解して、それを自らに具体的に応用するという「抽象化と具体化(の往復)」をやりたいと考えている人達なのです。
「具体と抽象」の関係は、文字通り2つに分けられる訳ではなくそれぞれに往復しながら使うのが、実用的?ともいっている。個人的には、それぞれの軸を持つことと前提条件を明確化することで「具体と抽象」を体系的に捉えやすくなると感じてます。
自分の場合は、どうしても具体的に捉えたくなる性格なため、どんな本を読んだとしても読み手がその内容をどう具体的に捉えたか?を重要視したくなります。そこは主観でいいと思っています。後は、読み手本人が実生活でどうそれを活かすかが重要なので。インプットだけでは、意味がないのでどんどんアウトプットして行く中で洗練されていくのでしょう!
是非、人間関係に悩んでいる人にはオススメの本です。文庫なので価格もリーズナブルですから会社が休みの時に涼しい部屋で読書しませんか!